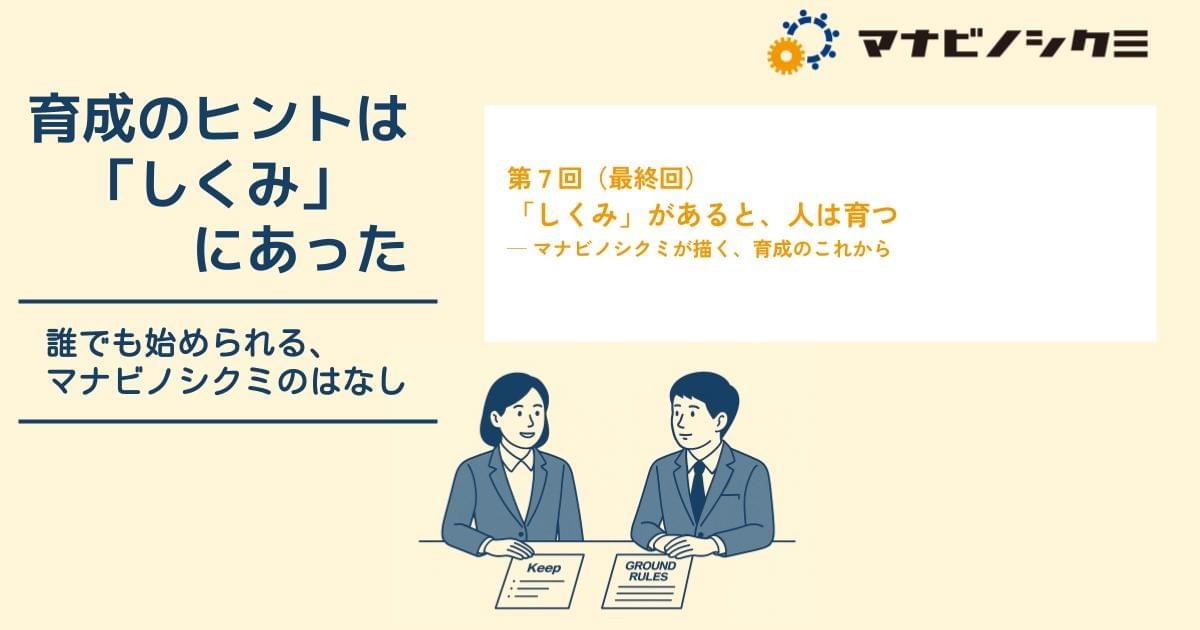
「後輩を育てるのって、結局センスですか?」
あるメンターが、そうこぼしたことがありました。
わかります。
育成は、一筋縄ではいかないし、正解もない。
しかも本業もこなしながら、手探りでなんとかやってるというのが現実です。
でも、「しくみ」があると、話は変わってきます。
育成のしんどさは、しくみで軽くなる
この連載では、「マナビノシクミ」の要素を少しずつご紹介してきました。
- 第1回| 「育成がしんどい」のは、あなたのせいじゃない
- 第2回| 「問い」があるから、人は考える
- 第3回| 「育つ場」は、日常に織り込める
- 第4回| 「教えない」ことで、育てることもある
- 第5回| 「意味」がわかると、人は動く
- 第6回| 「実験」が学びを加速する
こうしてふりかえってみると、「マナビノシクミ」は決して特別なテクニックではなく、誰もがすでにやっている育成のスタイルに名前をつけただけなのだとわかります。
育成の現場で、起きた変化
実際にマナビノシクミを取り入れた現場では、こんな変化が起きてきました。
- 1on1が、「報告の場」から「考える場」に変わった
- 日報に「意味」を見出すことで、言葉の質が変わった
- KPTAで「関係性」をふりかえり、信頼が深まった
- Actionが「やらされ」じゃなく、自分のチャレンジになった
そして育成者自身も、こう語っています、
「育成が個人の責任じゃなく、仕組みで支え合えるものだと思えるようになった」
マナビノシクミの全体像(ふりかえり)
あらためて、マナビノシクミの全体像を整理してみましょう。
問いを立てる
- 主体性を引き出す「問い」から始める
- 自分で考え、目的意識を持つ
ふりかえりをする
- KPTAなどを使って成功/失敗から学ぶ習慣がつく
- 次のチャレンジを自分で決める
意味を共有する
- 「なぜやるのか」を対話で共有
- 自分ごととして納得し、行動する
日常に織り込む
- 業務に「育成の種」を織り込む
- 現場で自律的に実践し、改善する
関係性を整える
- KPTAで関係性もふりかえる
- 心理的安全性と信頼が育つ
これらが組み合わさることで、育成の「偶然性」や「属人性」が減っていきます。
育成は「しくみ」でまわる。しかも、あなたの現場から
「マナビノシクミ」は、誰かの特別な理論ではなく、忙しい現場で育成に向き合ってきた人たちの知恵から生まれました。
だからこそ、いま行っている育成活動にも無理なく組み込める。
大がかりな制度も、特別なツールも要りません。必要なのは、ほんの少しの「問い」と「仕組みを仕込む勇気」。
それだけで、現場は変わりはじめます。
最後に──あなた自身の育成も、しくみの一部です
この連載を読んでくれたあなた自身も、きっと「育成のただ中」にいる方だと思います。
育てる人は、同時に育っている人でもあります。
マナビノシクミは、そんな育成者自身の「ふりかえり」にも効くしくみです。
- 自分の問いかけは、相手にどのように届いているだろうか?
- 最近、意味を共有する対話ができただろうか?
- 関係性は、安心できる状態に近づいているだろうか?
ふりかえりながら進むことで、育成はつながっていきます。
育成を、「センス」から「シクミ」へ。
今日から、あなたの現場でも、マナビノシクミを小さく始めてみませんか?
