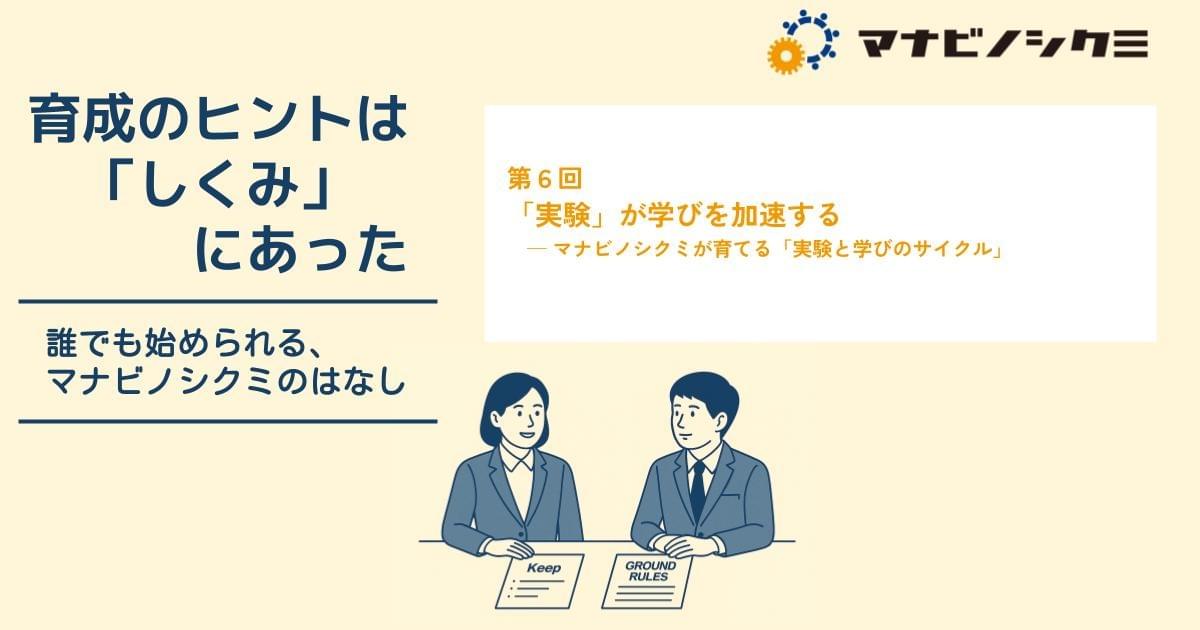
「ちゃんと教えたのに、うまくいかなかったんですよ」
「自分なりに考えて動いてくれたけど、結果が出なかった」
「どこまで任せていいか、正直わからない…」
育成をしていると、こうした「うまくいかない経験」に必ず出会います。でも実は、マナビノシクミが大事にしているのは、「失敗しないようにすること」ではなく、「失敗から学べるようにすること」なんです。
育成に「正解」は、ない
そもそも、育成において「正解」って何でしょうか?
相手によって理解の仕方も違えば、状況によってうまくいく方法も変わります。
つまり、育成とは本質的に実験の連続です。
- どこまで任せるか?
- どんな伝え方が響くか?
- どのタイミングでフィードバックするか?
すべてが「試して、ふりかえって、また試す」の繰り返し。そのサイクルを設計しておくことが、育成のしくみです。
事例①:ふりかえりを習慣化した若手チーム
ある職場で、若手チームが「1週間の小さな実験」を定着させました。
週の初めに「今週、ちょっとやってみたいこと」を各自が宣言。
金曜日には、その結果をKPTA(Keep/Problem/Try/Action)の形でふりかえります。
最初のうちは、「失敗したことを言っても大丈夫かな」「こんなこと話してもいいのかな」とためらいがちだった若手メンバーたち。
でも、メンターが繰り返しこう伝えました。意味づけをしたのです。
「うまくいかなくても大丈夫。チャレンジしたことに意味がある」
「ここは報告の場じゃなくて考える場だから、安心して言っていいよ」
そうやって、小さな対話を重ねていくうちに、少しずつ空気が変わっていきました。
ある若手は、こんなふうに語ってくれました。
「最初は評価されるかもって緊張してたけど、今は気づきや学びを持ち寄る場なんだなと思えるようになりました」
事例②:KPTAで関係性をふりかえる
実はこのチームでは、業務や行動のふりかえりだけでなく、「メンターと自分の関係」についてもKPTAでふりかえることを試しました。
メンターとの1on1で、こんな会話がなされました:
- Keep:意見を最後まで聞いてくれるところが、安心できている
- Problem:うまく話せないときに、焦ってしまうことがある
- Try:話す前に「ちょっと整理させてください」と言ってみる
- Action:1on1のグラウンドルールに、「考える整理する時間を歓迎する」を追加する
こうした会話を通して、育成そのものも対話のテーマになっていったのです。
そして見えてきた共通の気づきを、メンターと被育成者でグラウンドルールとして明文化していきました。
たとえば
- 途中でうまく話せなくなっても、焦らず整理する時間をとってOK
- 違う視点が出ても否定せず、まず「新しい視点をありがとう」と返す
- Tryは確約ではなく実験のアイデア
このように、ふりかえりが信頼を育て、それがグラウンドルールとして共有されることで、心理的安全性は着実に高まっていったのです。
リフレクションの流れで、学びを深める
この流れは、コルブの経験学習サイクルそのものです
- 具体的経験:どんなことをやったのか?
- 省察:どこがうまくいったか?/いかなかったか?
- 概念化:何が学びとして抽象化できるか?
- 試行:次はどう活かすか?/どんな行動にするか?
この4ステップに沿って問いかけるを設計しておくことで、「気づいて終わり」ではなく、次の一歩につながるふりかえりになるのです。
育成は、結果を問う場ではなく、「関係を育てる場」でもある
育成対象者が失敗したとき、つい成果や正しさに目が向きがちです。
でも、試行の過程に目を向けると、こんな問いが生まれます:
- 今回の工夫は、どんな意図があった?
- うまくいかなかったとき、何に気づいた?
- 次は、どう試してみたい?
そしてそれらのやりとりは、関係性をふりかえり、整え、信頼を深めるための問いにもなっていきます。
次回予告:「しくみ」があると、人は育つ
次回はいよいよ最終回。
ここまで取り上げてきた「マナビノシクミ」の各要素がどうつながり、育成の場をどう変えていくのか――
事例とともに、全体像を整理してお届けします。