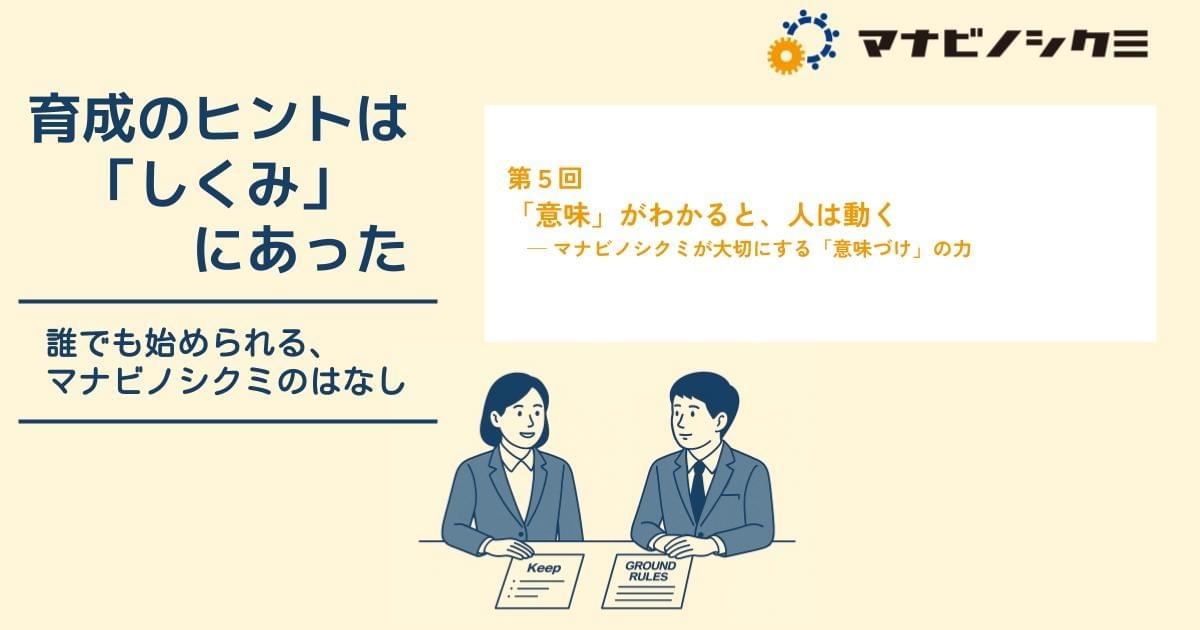
「この仕事って、なんのためにやってるんですか?」
新人や若手から、こう聞かれてドキッとした経験、ありませんか?
「それ、説明しなきゃいけないの…」と思う反面、たしかにうまく答えられないことももある。
これは育成において、「意味づけが抜けている」サインかもしれません。
「やらされ感」の正体は、「意味がわからない」こと
マニュアル通りに業務を教えていても、相手にとってその作業の意味がつかめていなければ、やる気も続きにくいものです。
- どうしてこれを今やるのか
- この仕事が、誰に、どう役立っているのか
- 自分がこの仕事を通して、どう成長するのか
こうした意味づけがないまま進むと、育成対象者はただ「指示をこなす人」になってしまい、成長の実感も持てません。
事例:「日報」が意味を持った瞬間
ある現場で、若手が「日報って、誰が読んでるんですか?」と質問してきました。
実はその若手、日報を書くことに少しモヤモヤを感じていたそうです。
「これって、上司に自分の行動を監視されてるだけじゃないの?」と、そんなふうに思っていたのです。
そこで先輩がこう伝えました。
「この日報は、翌日のシフト担当や工程リーダーが見て、翌日の配置や支援を決める材料にしてるんだ。
つまり、あなたの視点や判断が、チームの動きを支える判断材料になっているってことだよ」
その瞬間、若手の表情が変わりました。
「じゃあ、自分の観察や気づきが、次の仕事を左右してしまうのですね…」
それ以降、その若手が書く日報には、現場の変化や工夫、改善の提案が自然と含まれるようになりました。「意味」がわかるだけで、人の行動は変わる。しかもそれは、ただ従わせるよりもずっと、自然で力強い変化でした。その後、翌日のシフト担当や、工程リーダーが、彼を見る目も変わってきました。
意味づけのための問い
マナビノシクミでは、以下のような問いを活用して、育成対象者と「意味」を言葉にする時間をつくります。
- この仕事は、誰に、どんな価値を届けている?
- これを丁寧にやることで、どんな未来につながる?
- 自分はこの仕事を通して、どんな力を伸ばしたい?
作業が目的や意義とつながったとき、人は「やらされる人」から「自ら動く人」に変わっていきます。
育成者自身も、意味を言葉にできるか?
この回は、育成対象者だけでなく、育成する側にも問いが返ってくる回かもしれません。
- この仕事って、自分にとってどんな意味がある?
- このチームで育てるって、どんな未来につながる?
- 自分はなぜ、今この役割を引き受けているんだろう?
意味は、育成対象者に教えるものではなく、一緒に言葉にしていくものです。
次回予告:「実験」が学びを加速する
次回は、マナビノシクミの特徴である「実験とふりかえりのサイクル」に焦点を当てます。
- 育成に「完璧な正解」は必要なのか?
- 小さなトライ&エラーがチームを育てる理由とは?
実際の現場でのふりかえりの事例もご紹介します。