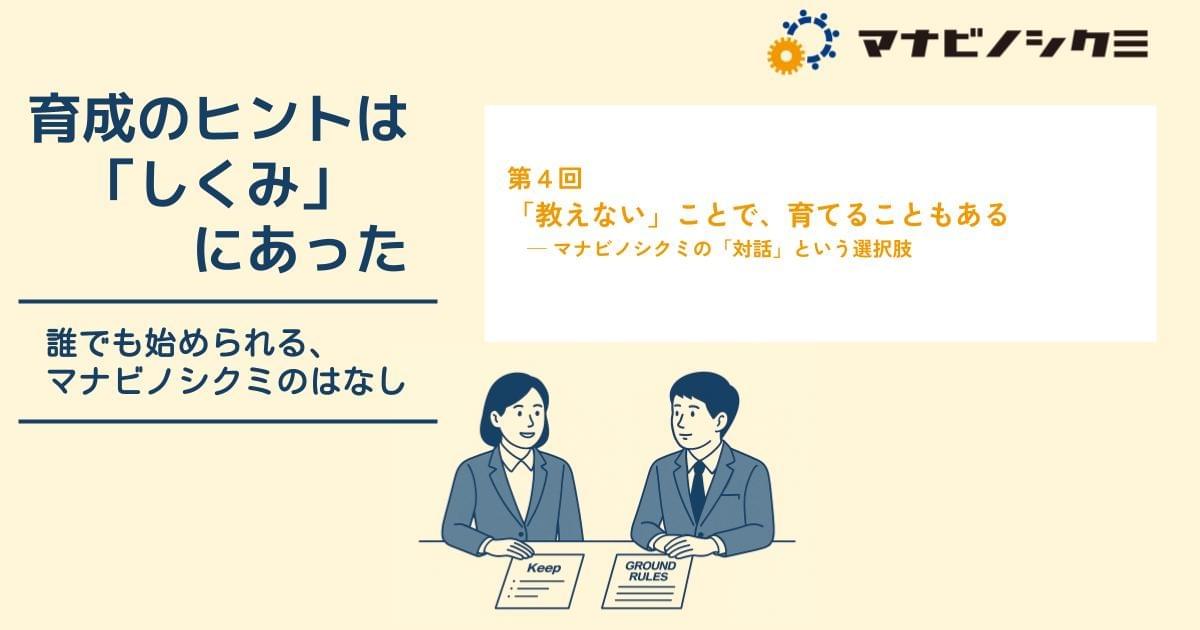
「どうしても、教えすぎちゃうんですよね」
「沈黙に耐えられなくて、つい先に言っちゃう」
「質問されたら、すぐに答えないといけない気がして…」
メンター経験がある方なら、一度はこんな場面に心当たりがあるのではないでしょうか。
もちろん、教えることが悪いわけではありません。
でも、教えすぎが相手の「考える機会」を奪ってしまっているとしたら…?
今日は、そんなときに試したい、「教えない勇気」と「対話のあり方」についてお話しします。
育成は「正解を教える」ことじゃない
育成の現場では、どうしても「知っている人が教える」「経験がある人が導く」構図になりがちです。
でもその構図が強すぎると、育成対象者は「自分で考える前に、答えをもらう」ことに慣れてしまいます。
結果として、「答えがなければ動けない人」が育ってしまうリスクもあります。
マナビノシクミでは、この点に注目し、育成者の役割をこう捉え直しています:
「教える人」ではなく、「問いを持ち、共に考える人」
つまり、「対話する人」です。
事例:「問い」で、行動が変わった面談
ある営業所のメンターが、いつもの面談スタイルをガラッと変えました。
具体的なアドバイスをあえて控え、リフレクションの流れに沿って問いを投げるだけのスタイルにしたのです。
こんな問いを使っていました:
- 具体的経験(Concrete Experience)
「その時、何が起きた?」「自分はどんな行動をした?」 - 省察(Reflective Observation)
「どう感じた?」「うまくいったこと、いかなかったことは何だった?」 - 概念化(Abstract Conceptualization)
「それって、他の場面でも応用できそう?」「今回の経験から、どんなことが言える?」 - 試行(Active Experimentation)
「次に似た状況が来たら、どうしてみる?」「どんなふうにやってみたい?」
この面談のあと、育成対象者がこう言いました。
「あの時間のおかげで、自分で考えるってこういうことか、初めて実感しました」
翌週からは、自分で問いを立てて動くようになったそうです。
対話のポイントは「聴く」「待つ」「問いかける」
対話を育成に取り入れるとき、大事なのは3つの姿勢です。
聴く
「それってどういうこと?」「もう少し教えてくれる?」と、興味を持って耳を傾ける。
待つ
沈黙を恐れない。相手が言葉を探す時間を「奪わない」。
問いかける
経験を引き出し⇒気づきを言語化し⇒概念化し⇒次の一歩を具体化する、というリフレクションの流れに沿った問いを使う。これだけで、会話の重心が「教える側」から「育つ側」へと移っていきます。
小さな「問い」が、自ら考える習慣を育てる
「ちゃんと教えてあげなきゃ」と思っていた育成者が、少し対話のスタンスに変えれば、相手が考え始める。
その変化は、育成対象者だけでなく、メンター自身の余裕や関わり方にも良い影響を与えます。
「何も教えてないのに、相手が自分で動き出した」
そんな瞬間が生まれたら、ちょっと嬉しくなりませんか?
次回予告:意味がわかると、人は動く
次回は、「意味づけ」がテーマです。
- 「この仕事って、なんのためにやってるんですか?」という問いに、どう答える?
- 育成対象者の「やらされ感」を減らすには?
- 仕事の意味を伝える、具体的な事例もご紹介します。