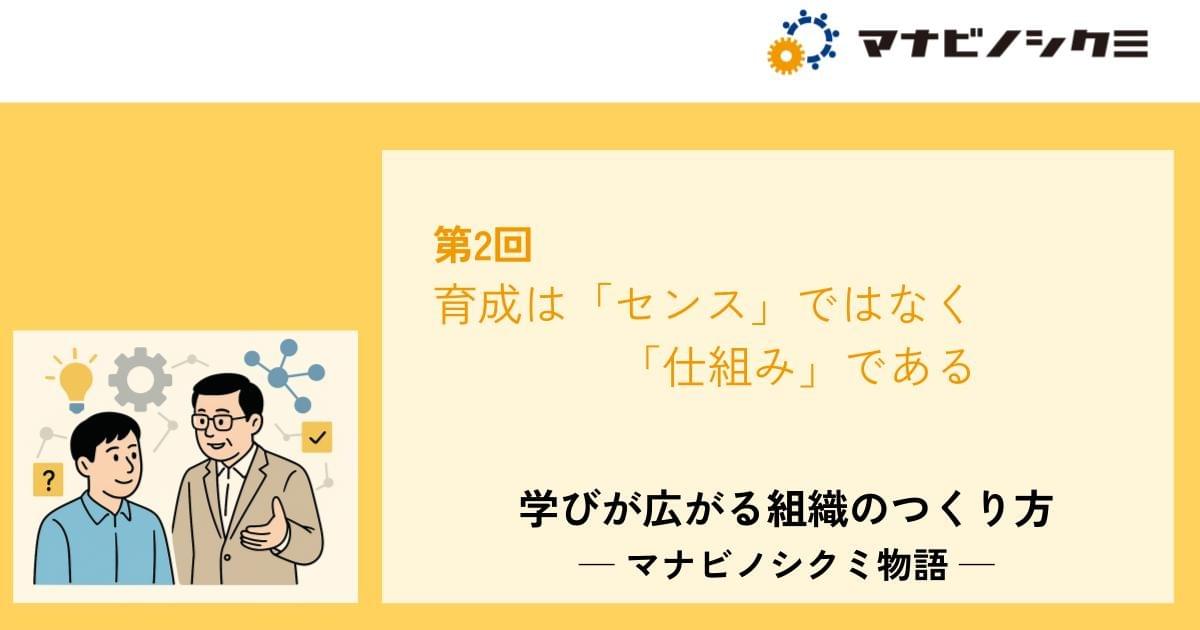
多くの組織では、人材育成を特定の優秀な人や、経験豊富なベテランの「センス」に頼りがちです。しかし、それでは属人化が進み、組織全体の成長速度が鈍化してしまいます。「マナビノシクミ」は、こうした課題を解決するために、「育成は誰もが実践できる仕組みである」という考え方を提唱します。
この考え方に基づき、優秀な個人のスキルを組織の共通財産へと昇華させる手法を提供します。育成の成功を偶然に頼るのではなく、再現可能なプロセスとして設計することで、継続的な組織の発展を可能にします。上司は、部下の才能を信じ、その成長を促すための「先行投資」として、この仕組みを導入する決断を下すのです。
事例:前回、内向的なユウキが、DXツール開発の成功ノウハウをうまく言語化できず、悩んでいることをお伝えしました。彼の貴重な経験を組織の財産にするため、彼の上司が下した決断とは何だったのでしょうか。
ユウキの上司であるタナカ部長は、彼のDXへの貢献を高く評価していました。しかし、ユウキが自分のノウハウをうまく言語化できないことに、タナカ部長は危機感を覚えていました。「ユウキのスキルを、チーム全体の力に変えなければならない」。そう考えた彼は、人材育成に関する情報を集め始めました。
そこで彼が見つけたのが「マナビノシクミ」のコンセプトでした。特に「育成はセンスではなく、仕組みである」という言葉が心に響きました。「特定の誰かが教えるのがうまい、という話ではない。誰にでもできる体系的な方法論があるのなら、ユウキにそれを身につけさせ、彼の成功をみんなのものにできる」。
タナカ部長はユウキを呼び出し、「君のDXの成功を、みんなで分かち合おう」と声をかけました。そして、「マナビノシクミ」の研修を彼に勧めました。ユウキは最初は戸惑いましたが、それは自分への期待の証だと感じ、挑戦することを決意しました。この上司の決断は、ユウキの個人的な成長を促すだけでなく、組織全体のDX推進を加速させるための、まさに戦略的な一歩だったのです。タナカ部長は、この投資が未来の組織のあり方を変えるものだと確信していました。
次回:第3回『経験を「知識」に変える「ふりかえり」の力』に続く