·
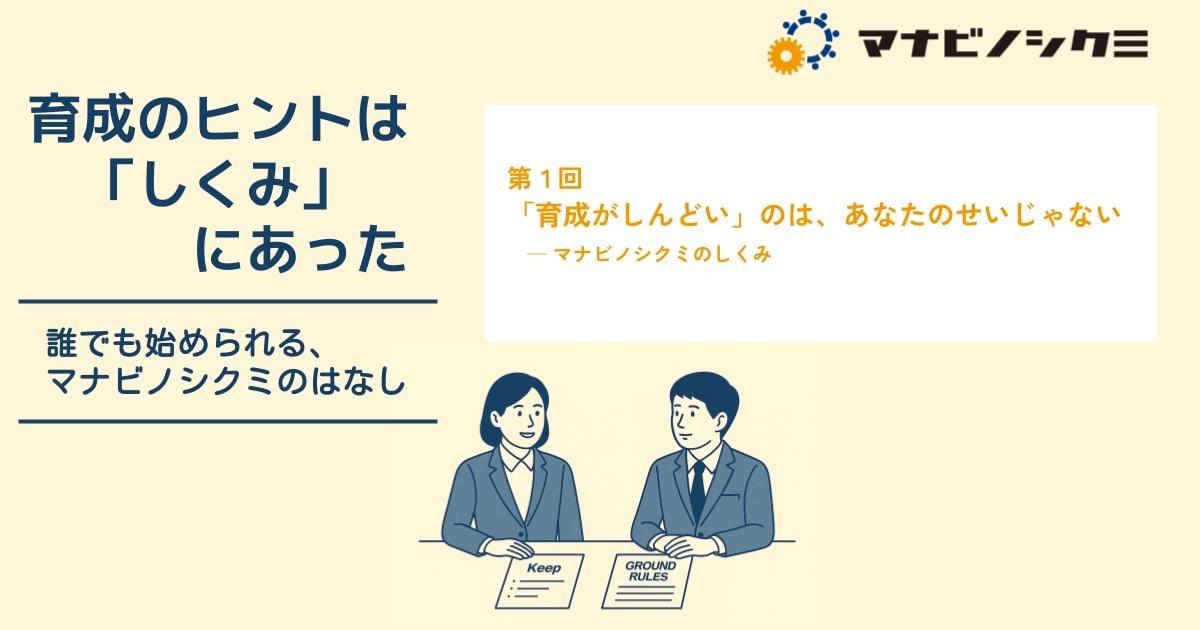
「本業だけでも大変なのに、育成もやらないといけないんですよね……」
「自分が忙しくて余裕がないと、つい後輩に冷たくしてしまって落ち込む」
「このままじゃ、後輩に追い抜かれちゃうんじゃないかと焦ることもある」
これは、実際に現場で育成を担う方々から聞いた言葉です。
育成にまつわる「しんどさ」は、決してその人の怠慢やスキル不足のせいではありません。むしろ、育成を「個人のがんばり」に任せすぎている仕組みの問題だと、私たちは考えています。
「人が育つ」には、育成者の熱意だけでは足りない
育成がうまくいかないとき、育成者自身が「自分の関わり方が悪いのかも」と自責に陥ってしまうことがあります。
でも実は、育成の現場にはこんな構造的な課題があります:
- 本業と育成の両立で手一杯になりがち
- 自分なりに頑張っても評価されにくい
- 後輩がうまく育たないと、プレッシャーになる
- 一方で、「ちゃんと育てたい」という気持ちはある
この葛藤が、育成のしんどさを生んでいます。
「マナビノシクミ」は、育成の負担を「しくみ」で支える
私たちが提案する「マナビノシクミ」は、こうした育成の負担を、「関わり方」と「環境のデザイン」で軽減するしくみです。
キーワードは、「しくみ」。
具体的には、以下のような要素を組み合わせて、育成を支援します
- 問い
相手の内省を促す、成長の起点となる問い - 場
学びが自然に生まれる、安心・対話・ふりかえりのある空間 - 対話
答えを教えるのではなく、共に考えるやりとり - 意味づけ
仕事の価値や背景を伝え、「やらされ感」からの脱却 - 実験とふりかえり
小さく試して、内省し、次につなげる学びの循環
これらはすべて、「特別なスキルや時間がなくてもできる」ように設計しています。
育成は「人生に関わる営み」である
育成とは、単なる仕事の引き継ぎではなく、誰かのこれからの人生に関わる深い営みです。軽く扱えるものではありません。
- 最初に出会った育成者の関わり方
- かけられたひと言
- 一緒に悩んだ時間
こうした経験が、その人のこれからの「働き方」や「人との向き合い方」に長く影響を与えます。だからこそ、育成の現場には、行き当たりばったりな熱意や根性だけではなく、しくみで支えることが必要なのです
次回予告:「問い」があるから、人は考える
第2回では、「マナビノシクミ」の中核をなす要素のひとつ、「問い」についてご紹介します。
- なぜ、問いがあると後輩は自分で考え始めるのか?
- 忙しい現場でもできる問いかけの工夫とは?
- 「問いによる育成」で、実際に起きた変化の事例
などを、わかりやすくお届けします。
