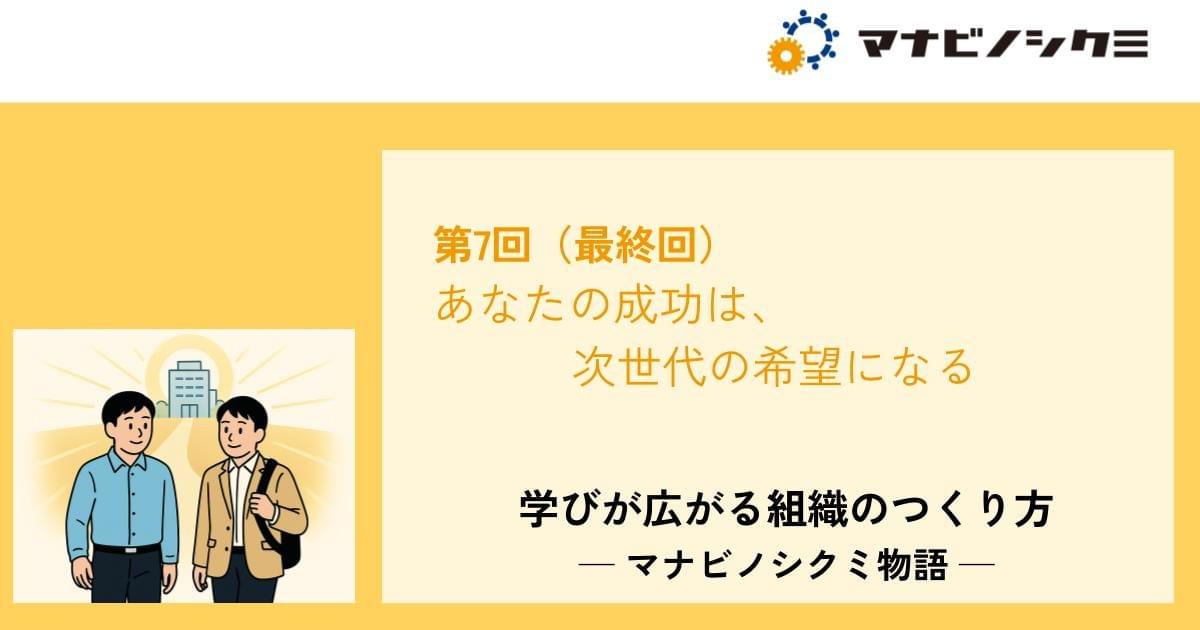
「マナビノシクミ」の導入は、単なる人材育成ではなく、組織の未来への投資です。個人の成功が組織の共通財産となり、それが次世代の成長を支える基盤となります。
私たちは、日々の業務の中で多くの成功や失敗を経験します。しかし、それが単なる「出来事」として流されてしまうのは、もったいないことです。その経験を「マナビノシクミ」で体系化することで、それは揺るぎない知識となり、あなたの成長を加速させるとともに、次世代の希望となります。
事例:前回、育成者としての新たな目標を見つけたユウキ。彼が率先して学びを共有するようになったことで、組織はどのような変革を遂げたのでしょうか。
ユウキの部署には、「ふりかえり」が日常の習慣として根付き始めました。以前は、トラブルが起きても「なぜそうなったのか」を考えることなく、その場しのぎに対処するだけでした。しかし今では、問題が起こるたびに自然とKPTAのフレームワークが使われるようになり、Problemを考える前にKeep考える事が根付き始めました。思考がポジティブになることで「次はこうしてみよう」という改善策が次々と生まれるようになりました。
チームメンバーは、以前よりもオープンに意見を交わすようになり、成功体験だけでなく、失敗からも学びを得る文化が生まれました。ユウキ自身も、人前で流暢に話すことは相変わらず苦手ですが、自分の言葉で誰かの役に立てることが、何よりも大きな自信につながっています。
ユウキの小さな一歩がきっかけとなり、組織の風土は加速度的に改善されていきました。その成果は、タナカ部長の部署評価にも反映され、彼は「先見の明がある管理職」として周囲から一目置かれるようになりました。さらに、この部署の成功はHR部門の目にも留まりました。彼らは、ユウキのような若手社員が自律的に成長し、組織全体の改善に貢献している姿を高く評価し、全社的な人材育成プログラムとして「マナビノシクミ」の導入を検討し始めました。
社内に「マナビノシクミ」のコミュニティが立ち上がったのは、それから間もなくのことでした。ユウキが部署内で始めた「ふりかえり会」に、他の部署の社員が見学したいと声をかけてきたのです。営業、マーケティング、企画、エンジニア。これがきっかけとなり、職種も役職も関係なく、自分の「学び」を共有し、お互いの課題を解決するためのヒントを交換する場が自然発生的に生まれました。このコミュニティは、互いの強みを活かし、弱みを補い合う「互助」の精神で満ちています。
ここまで読んでいただいた方へ: DXで小さな成功を収めたあなた。その経験は、決してあなただけのものに留めておくべきではありません。そのノウハウを「マナビノシクミ」で体系化し、誰かに伝えてみませんか?あなたの小さな一歩が、きっと組織の未来を動かす力になります。